HPV(子宮頸がん予防)ワクチン接種のお知らせ
HPV(子宮頸がん予防)ワクチン接種について
子宮頸がんは、ウイルス感染で起こるがんの一つで、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と考えられています。HPVワクチンは、子宮頸がんを起こしやすいタイプのHPV16型と18型で、子宮頸がんの原因の50から70%を防ぎます。
HPVワクチン接種は、厚生労働省の勧告に基づき平成25年6月から積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3年11月から積極的な勧奨が再開されています。
また、積極的な勧奨の差し控えにより公費での接種機会を逃した方に対し、公平な接種機会確保する観点からHPVワクチンの接種の機会が設けられました(キャッチアップ接種)。
つきましては、下記に添付しました厚生労働省のホームページをご覧いただきますようお願いします。
厚生労働省HP「ヒトパピローマウイルス感染症から子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチンから」
対象者
- 小学校6年生から高校1年生相当年齢の女性
- キャッチアップ接種対象者
(接種は合計3回で、完了するまでに約6か月かかるため、接種を希望する方は、お早目の接種をご検討ください。)
キャッチアップ接種対象者(令和7年度まで延長)
- 令和7年度は、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性
- 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方
※キャッチアップ接種について、詳しくはこちらをご確認ください。
接種方法
- 実施医療機関に直接予約をする。
- 母子健康手帳を持参し、医療機関で同じワクチンの種類の予防接種を3回受ける。
医療機関はこちらのページ「子どもの予防接種」から「予防接種委託医療機関一覧」をご確認ください。
県外の医療機関で予防接種をされる場合
事前に申請が必要ですので、接種2週間前までに健康推進課までに到着するように提出してください。接種される医療機関名、接種回数も忘れずに記入ください。
県外接種依頼書交付申請書の様式は、こちらのページ「申請書ダウンロード」をご覧ください。
接種スケジュール
HPVワクチンは2価ワクチンと4価ワクチンと9価ワクチンの3種類があります。
原則として、同じ種類のワクチン接種をすることをお勧めしますが、医師と相談のうえ途中から9価ワクチンに変更し残りの接種を完了することも可能です。
9価ワクチンを任意接種で完了している人は接種する必要はありません。
キャッチアップ接種対象者の人は、未接種分を接種します。
| 種 類 | 回数 | 標準的な接種間隔 |
標準的な接種間隔で接種できない場合 |
|
|
サーバリックス (2価) |
3回 | 1回目 | 初回接種 | 初回接種 |
| 2回目 |
初回接種から1か月後 |
2回目は1回目から1カ月以上あけて、 3回目は1回目から5カ月以上かつ2回目から2カ月半以上あける |
||
| 3回目 |
初回接種から6カ月後 |
|||
|
ガーダシル (4価) |
3回 | 1回目 | 初回接種 | 初回接種 |
| 2回目 |
初回接種から2か月後 |
2回目は1回目から1カ月以上あけて、 3回目は2回目から3カ月以上あける |
||
| 3回目 |
初回接種から6か月後 |
|||
|
シルガード (9価)
15歳未満の方は 2回または3回接種が可能
|
3回 | 1回目 | 初回接種 | 初回接種 |
| 2回目 |
初回接種から 2か月後 |
2回目は1回目から1カ月以上あけて、 3回目は2回目から3カ月あける |
||
| 3回目 |
初回接種から 6か月後 |
|||
| 2回 | 1回目 | 初回接種 | 初回接種 | |
| 2回目 |
初回接種から6か月後 |
2回目は1回目から少なくとも5カ月以上あける 但し、2回目が5カ月未満の場合は3回接種が必要。3回目は2回目から3ヵ月以上あける |
||
接種料金
接種対象者の年齢であれば無料で接種できます。
期限を過ぎると全額自己負担となります(1回約16,000円から26,000程度)。
接種の際に必要なもの
- 母子健康手帳
- 予診票
市内の契約医療機関・市外で手続きが不要な医療機関にもあります。 - 健康保険証
注意事項
- この予防接種による期待される効果や、予想される副反応等について、接種を受ける本人もよく理解して受けてください。ご不明な点はかかりつけ医(接種医療機関)にお尋ねください。
- 13歳以上16歳未満の場合、予診票・同意書に保護者が署名することにより、お子さまだけでの接種も可能ですが、急な体調変化を来たす恐れもあるため、保護者の同伴をお勧めします。16歳以上の方は、保護者の同意の必要はなく、本人の同意により予防接種を受けることができます。必要に応じて、保護者の同意をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-33-4252
ファクス:0748-34-6612
メールフォームによるお問い合わせ
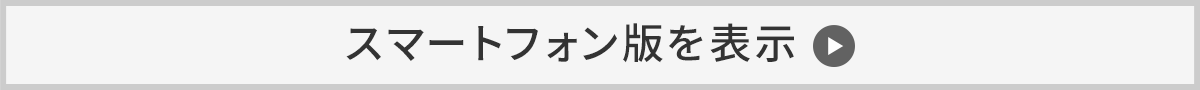
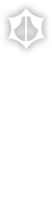




更新日:2025年04月01日