介護保険のサービス
介護(予防)サービス計画
要介護と認定された人が在宅でのサービスを適切に利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画を作成し、サービス提供事業者との調整などを行います。
要支援と認定された人は、近江八幡市 介護予防支援事業所の保健師などの専門家が介護予防サービス計画を作成し、サービス提供事業所との調整などを行います。
いずれの場合も、計画の作成には利用者の負担はありません。
在宅サービス
要支援または要介護の認定を受けた人が利用できます。
居宅サービス
訪問介護[ホームヘルプサービス](要介護1以上に認定された方)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事などの身体介助や、炊事、掃除などの生活援助を行います。
(食事の準備等の生活援助は、原則、独居の人のみ利用可)
(介護予防)訪問入浴介護
介護福祉士や看護師などが自宅を訪問して、入浴の介護を行います。
(介護予防)訪問看護
看護師や准看護師などが家庭を訪問し、医師の指示にもとづいて、療養上の世話と診療の補助を行います。
(介護予防)訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、機能訓練(リハビリテーション)を行います。
(介護予防)居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護[デイサービス](要介護1以上に認定された方)
通所介護施設で、入浴、食事の提供や機能訓練などのサービスを日帰りで行います。
- 小規模な通所介護(指定定員数18人以下)は、平成28年4月1日より「地域密着型通所介護サービス」へ移行しました。
(介護予防)通所リハビリテーション[デイケア]
介護老人保健施設などに通所し、主に心身の機能の維持回復を図るために機能訓練を行います。
(介護予防)短期入所生活介護[ショートステイ]
特別養護老人ホーム等に短期間入所して、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを行います。
(介護予防)短期入所療養介護[医療型ショートステイ]
介護老人保健施設や介護医療院に短期間入所し、看護・医学的管理のもとで介護や機能訓練などを行います。
(介護予防)特定施設入居者生活介護
特定施設(有料老人ホームなど)で入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練、療養上の世話を行います。
地域密着型サービス(本市に事業所がないサービス種類については省略しています)
・本市の介護保険被保険者が利用できます。
地域密着型通所介護(要介護1以上に認定された方)
通所介護施設で、入浴、食事の提供や機能訓練などのサービスを日帰りで行います。(定員数18人以下)
(介護予防)認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に、通所介護施設において専門的なケアを行います。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
通いを中心に利用者の選択に応じて、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを行います。
看護小規模多機能型居宅介護(要介護1以上に認定された方)
小規模多機能型居宅介護に加え、訪問看護のサービスも行います。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護[認知症グループホーム](要支援2以上に認定された方)
認知症高齢者が、9人で共同生活をしながら、介護者から入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などのサービスを行います。
・本市の介護保険被保険者になって1年以上の方が利用できます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上に認定された方)
居宅の生活への復帰を念頭に置いて、要介護者である入所者の要介護状態の軽減または悪化の防止を助けるように、心身の状況等に応じて入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練等のサービスを行います。
・本市の介護保険被保険者になって1年以上の方が利用できます。
その他のサービス
(介護予防)福祉用具貸与
車いすやベッドなど日常の介護に適した福祉用具が借りられます。
対象種目
- 手すり(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
- スロープ(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排せつ処理装置
- 5から12については、原則要介護2以上と認定された人のみ対象となります。
- 13については、原則要介護4以上と認定された人のみ対象となります。(尿のみを自動的に吸引できるものを除く)
(介護予防)特定福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を特定福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合、購入費の一部を償還払いにより支給します。
同一年度(4月から翌年3月)で対象費用10万円を上限に購入に要した費用の7割から9割相当額を償還払いにより支給します。
対象種目
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉杖を除く)
・6から8については福祉用具貸与との選択制です。
(介護予防)住宅改修費支給
自宅で生活しやすいよう住宅を改修する場合、要介護状態区分にかかわらず、同一人物・同一住宅(住民票記載の住所)に限り対象費用20万円を上限に改修費の7割から9割相当額を償還払いにより支給します。
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材等の変更
- 引き戸等への取替え
- 洋式便器等への便器の取替え など
改修の前に事前申請が必ず必要です。事前申請をするときに、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成する理由書が必要です。居宅介護支援事業所へ依頼してください。
施設サービス
要介護1以上に認定された人が利用できます。
介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
日常生活で常に介護が必要で、家庭において適切な介護が困難な場合に入所し、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練、療養上の世話などを受けます。
平成27年4月以降、新たに入所するためには、原則として要介護3から5の認定が必要です。
介護老人保健施設
病状が安定期にあり、入院治療する必要はないが機能訓練や介護、看護が必要なときに入所し、それらのサービスを受け、家庭への復帰をめざします。
介護医療院
病状が安定期にあるが長期間の療養が必要なときに入所し、医療、看護、介護等を受けます。
介護サービス利用にかかる費用
介護保険のサービスを受けたときは、原則として費用の9割・8割または7割が保険で給付され、1割から3割を自己負担します。
平成30年8月以降、65歳以上(第1号被保険者)で一定所得以上の人は、自己負担が3割に変わりました。
区分支給限度基準額
在宅サービスを利用する際には、要介護等状態区分別に介護保険から給付される上限額(区分支給限度基準額)が決められています。
利用額は要介護等状態区分やサービスの種類によって異なります。
| 要介護等状態区分 | 支払限度基準額 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
特定入所介護サービス費(介護保険負担限度額認定)
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院等及び地域密着型特別養護老人ホーム)に入所・入院(短期入所を含みます)される人で、所得の低い人には、居住費と食費の負担を抑えるために、申請により利用者の負担限度額認定証を交付します。
施設には平均的な費用(基準費用額)と負担限度額との差額が保険給付から支払われます。これを特定入所者介護サービス費(補足給付)といいます。
証の有効期間は、8月から翌年7月まで(新規申請の場合は申請月から次の7月まで)です。更新対象者には、毎年5月下旬を目途に通知をお送りします。自動継続ではなく、更新の手続きが必要です。
要件等の詳細は下記「申請書ダウンロード 介護保険 再交付・資格・認定・給付関係」ページ内の「負担限度額認定申請について」をご確認ください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減
社会福祉法人が提供する介護保険サービスをご利用の際に支払う利用者負担額が軽減される制度です。
ご利用の事業所に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示することにより利用料が軽減されます。(軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ適用されます。全ての社会福祉法人とそのサービスが対象となるわけではありません。)
要件等については下記「申請書ダウンロード 介護保険 再交付・資格・認定・給付関係」ページ内の「社会福祉法人の利用者負担軽減制度」をご確認ください。
軽減の申出をしている社会福祉法人については、下記の滋賀県ホームページ『8.申出をしている社会福祉法人等の一覧』をご覧ください。
高額介護(予防)サービス費の支給
介護サービス費用の1割、2割または3割は利用者が負担します(「利用者負担額」と言います)。世帯内での利用者負担額の合計が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が申請により払い戻される「高額介護(予防)サービス費」という仕組みがあります。
申請は初回のみとなり、以降は上限額を超えると申請時に指定された口座に支給します。
詳しくは下記「厚生労働省 介護サービス情報公表システム」よりご確認ください。
高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
介護保険と医療保険(国保、職場の健康保険、後期高齢者医療制度など)の上限を適用した後に、世帯内で1年間(8月から翌7月)の自己負担合計額が一定の限度額を超えた場合に、申請により超えた分が支給される制度があります。
詳しくは下記「厚生労働省 介護サービス情報公表システム」よりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
メールフォームによるお問い合わせ
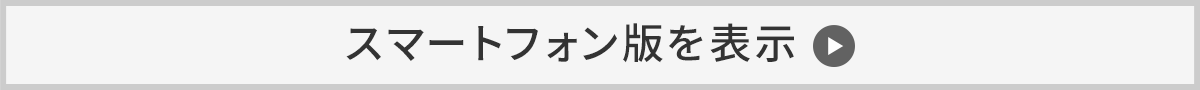
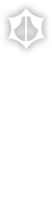




更新日:2025年03月18日