安田全男教育長からのメッセージ
パラダイム転換
安田全男教育長からのメッセージを以下のとおり掲載します。
パラダイム転換
近江八幡市教育長 安田 全男
この度、新たに近江八幡市教育長としてお世話になります安田全男です。何卒よろしくお願い申し上げます。
就任にあたりまして、私の教育観の一部や時代背景に関する私の認識を踏まえ、「子どもたちの生きる力」の涵養等について述べさせていただきます。
教育振興を図る大前提として、日本国憲法、教育基本法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、その他教育関連法に則ることはもちろん、国・県の教育振興基本計画などを参酌し、本市の教育大綱及び教育振興基本計画に基づき、子どもたちの命と安全を守り教育機会の保障に正面から取り組みます。
そのうえで、誰一人取り残されることのない地域に根差した本市固有の教育行政を、強い意欲をもって誠実に推進してまいります。
さて、時代背景についてであります。今日の世界情勢を見渡しますと、世界はVUCAの時代に突入しております。すなわち、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字をとったいわゆる「ブーカの時代」です。
これまで我々が社会の変化をとらまえ表現するとき、「少子化・人口減少や高齢化、グローバル化の進展、地球規模の課題、子どもの貧困、格差の固定化と再生産、地域間格差、社会のつながりの希薄化」などが声高に叫ばれてきましたが、これらの課題は実際にどこまで解決できているかは別として、ある程度予測し計画を立てそれなりに対応することができるものでした。
しかし、突発的に発生しました新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び突然勃発したウクライナ侵略等による国際情勢の急変は、今までの我々の予測常識を木っ端微塵に破壊し、いきなり人類を大変深刻な予測困難時代へと突き落したのです。そして我々は今、慌てふためいております。
このような予測不可能な危機、これまでの常識の範囲を大きく超え、敢えて考えることも想定することも社会全体で忌避してきたような危機にも、余裕をもって冷静に対応でき得る人材の育成が重要課題であると考えます。
少し振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響としては、国際経済の停滞、人的交流の減少、体験活動の機会の減少などの事態が生じ、全国の学校現場では、臨時休業せざるを得ませんでしたが、学校の子どもたちの居場所やセーフティネットとしての福祉的役割を再認識するとともに、これを契機として遠隔・オンライン教育が進展し、学びの変容がもたらされた面もありました。
これらのことから、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展は社会により良い変化をもたらす可能性のある変革として注目されてもいます。今後の社会を見据えたとき、現時点で予測される社会の課題や変化に対応して人材を育成するという視点だけでなく、予測できない未来に向けて自らが社会を創り出していくという視点での人材育成が是非必要となります。
まず、予測可能な課題としては、デジタル人材やグリーン(脱炭素)人材が不足するとの予測があります。
また、AIやロボットの発達により、特定の職種では雇用が減少し、今後は問題発見力や的確な予測、革新性といった能力が一層求められることや、労働市場の在り方や働く人に必要とされるスキルが今後変容し、生成AIは人々の暮らしや社会に大きな変革をもたらす可能性があることが指摘されています。
同時に、経済協力開発機構(OECD)の「学びの羅針盤2030」の6では、個人と社会のウェルビーイングは「私たちの望む未来(Future We Want)」であり、社会のウェルビーイングは共通の「到達地点」とされているところです。
すなわち、障害の有無や年齢、文化的・言語的背景、家庭環境などにかかわらず、誰一人取り残されることなく、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会の実現を目指し、その実現に向けた社会的包摂を推進する必要があります。こうしたことはすべてこれまでの常識で予測可能な課題であります。
一方、予測できない未来に向けて自らが社会を創り出していくという視点からは、すべての人々が普遍的価値を共有した上で、主体的な社会の創り手となる考え方が重要であります。今後目指すべき未来社会像として、持続可能性と強靭性を備え、地域住民の安全と安心を確保するとともに、一人一人が多様な幸せを実現できる、人間中心の社会としての「Society5.0」実現が求められています。
そのためには従来の意志決定過程PDCAモデルは通用しなくなっており、予測不可能な未来に対応するためには想定外の事態を絶えず観察・感知(Observe)し、それに基づき我々の立ち位置や状況を把握・判断(Orient)し、同時に最善の戦略戦術をすばやく決定(Decide)・対処(Act)するというOODAモデルの採用が不可欠であるといわれています。
こうした社会の現状や根本的な変化を踏まえたとき、教育こそが、社会をけん引するエンジンであり、教育に携わる関係者の責任はこれまでになく、極めて重く大きくなっています。
話は少し変わりますが、「量子コンピューター」が開発されたというニュースをお聞きになった方も多いと思います。
予測困難な時代を切り開く最先端の主役の一つがこの量子コンピューターに代表される「量子力学」と、その「トンネル効果」や「量子のもつれ・重ね合わせ」であるといわれています。
量子とは、粒子と波の性質を合わせもった、とても小さな物質やエネルギーの単位のことで、物質を形作っている原子そのものや、原子を形作っているさらに小さな電子・中性子・陽子といったものが量子の代表選手です。
その量子のトンネル効果とは、おおざっぱには、私たちの目に見える物質レベルの世界では、跳ね返されてしまう大きな障壁や転げ落ちてしまうほどの急峻な坂でも、目に見えない世界では、ごく小さなエネルギーでこれらの量子が障壁を難なくすり抜けたり、坂を乗り越えてしまったりという現象や挙動です。フラッシュメモリーは量子のこのトンネル効果を活用して情報を保存しています。
量子は、粒でもあり波でもある。また、異なる側面を合わせもって同時に存在し、離れた場所の状態と強く絡み合っている特性があるといわれています。量子コンピューターではこうした重ね合わせの特性を活用して量子ビットに「0」と「1」の両方の情報やそれ以上の情報が同時に保存され複雑な計算を迅速に行えると期待されています。
例えて申し上げるとこうした量子そのものがもつ特性、すなわち「多様な異なる情報を同時に把握し、流動する国際・国内情勢と強くつながり、前例のない大きな困難も小さなエネルギーですり抜け解決に導く」というような能力を、体系的な教育方針に沿って我々自身や子どもたちが獲得できないか。
具体的には、幼少期の早い段階から成長過程を通して、文学、音楽、絵画、芸術、スポーツ、歴史、語学、数学、物理、経済、など複数の分野に同時に興味関心を抱き、変容可能な専門性、柔軟性、協調性を合わせもった人材が育ってはじめて、予測困難な社会や世界を乗り越え結果、VUCAの時代を生き抜く力が養成されるものと考えます。
この意味するところは大きく、例えますと、我々のこれまでの常識は目に見える世界での物質レベルのニュートン力学(古典力学)に留まっておりましたが、予測不可能な時代、すなわち容易には目に見えない時代の変化に通用するものは、いわば量子力学レベルの常識でなければなりません。
こうしたパラダイム転換こそ、今求められている教育の方向性であり、国がめざすこうした教育改革の波動を、立場を異にする関係者間で互いに同期させることによってはじめてその転換が可能であると考えます。
その意味では、既に本市で取り組まれている保幼小中の滑らかな接続や読書活動等は、立場を異にする関係者が同期しなければ成し遂げられない取組であり、パラダイム転換の第一歩でもあります。さらなるステップとしては、リベラルアーツとしての音楽・芸術への新たな体系的な取組や人類学的視点で社会的沈黙を分析するアンソロビジョンを通じた人材育成の議論も、今後求められるのではないでしょうか。
いずれにいたしましても、こうした認識のもと、教育委員会における真摯な議論の積み重ねによる意思決定はもちろん、本市教育大綱等に則り、市長部局とも建設的に協議・連携し、近江八幡市としての一貫した教育行政の推進に、風通しよく、力強く、誠実に取り組んでまいる所存です。
どうか、皆様のご理解ご協力、ご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
PDF版は以下の添付資料をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号: (庶務グループ)0748-36-5539、(教育施設管理グループ)0748-36-5563
ファクス:0748-32-3352
メールフォームによるお問い合わせ
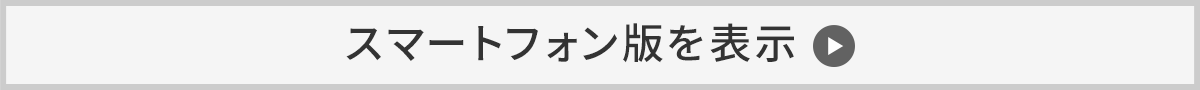
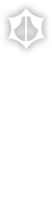




更新日:2024年05月27日